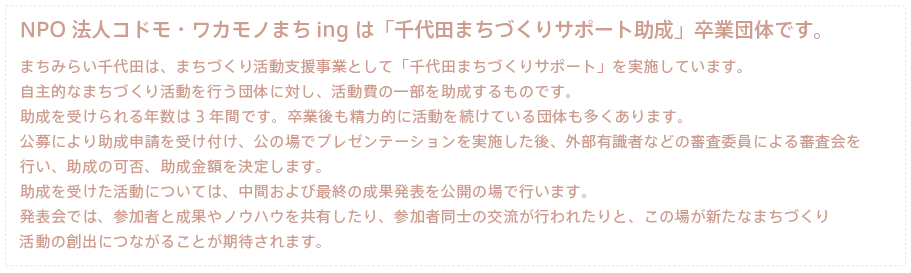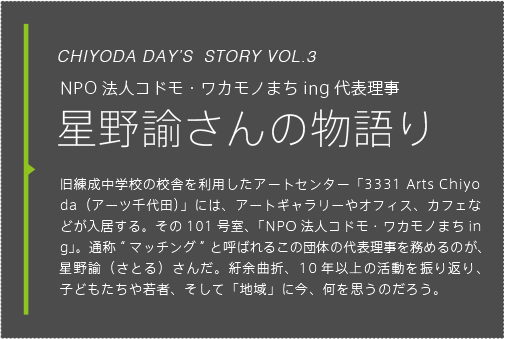始まりは、大学生による
空き屋“児童館”計画
コドモ・ワカモノまちingの前身は、大学生らによるボランティア団体だった。
千代田区神田の大学に通い、建築を学ぶ傍ら、子どもに関わるボランティア活動を行っていた星野さん。
運命を変えたのは、大学4年生のときに出会った『子供の参画』という著書。
本を読み終えた彼の中で、これまで別々のものだった「建築」と「子ども」が一つに合致した。
「すぐに出版社に電話して、著者に会わせてほしいと掛け合った」それほどの衝撃だった。
そして、一週間後に仲間とボランティア団体を立ち上げることを決める。
星野さんらボランティアメンバーは、それまで神田になかった児童館を作ることにした。
家賃交渉の末、空き家となっていた三軒長屋を破格で借り受け、町の工務店や取り壊し、中の家などから資材や必要な道具を調達。
地域の人たちの賛同と厚意のおかげもあり、わずか10万円の改修費で、空き家は放課後の子どもたちの遊び場に生まれ変わった。
一階を児童館スペースにし、二階は学生たちのシェアスペースとして貸し出すことで、家賃や運営費を捻出。次第に自分たちの団体だけでは運営が回らなくなり、近隣の他大学にも声をかけることにした。
児童館を始めてから地域の人たちにも認知されるようになり、最初は小さな点だった活動が神田以外の地域へも広がっていく。

避けられない資金問題
民間助成金が支えに
学生ボランティアから、2008年にNPO法人コドモ・ワカモノまちingになるにあたっては、
もちろん紆余曲折があった。
法人化のきっかけの一つは星野さんの結婚。
2008年、今の妻との結婚を機に、「一生かけて、本気でやりたいことだけをして生きてみよう」と
話し合い、NPO法人化。
ふたり揃って仕事を辞め、子どもと地域の人たちとの縁をつなぐ、子どもたちと遊び尽くす、
そんな生き方を選んだ。
しかしボランティア団体としての活動を続ける上で、無視できないのは資金の問題。
学生時代から「地域に子どもの居場所を」と思い描いてきた星野さんだが、継続するには
現実にも目を向けなければならない。
そんなとき、救世主となったのが民間助成金の存在。1年ないし3年などと期間が定められているが、
「助成金があったから今につながっていることは言うまでもない」という。
活動を始めて一年、二年、三年。年を経るごとにコドモ・ワカモノまちingに対する社会の
期待は大きくなり、受けられる支援も増えていった。
しかし、「助成金を受けられる期間には限りがある。その間に自立した資金繰りの仕組みを確立するのは大変なこと」と星野さん。
そう憂慮しながらも、受けられる助成金の額が増えてきていた中、ふと気づいたことがある。
「お金の管理や企画書の作成にばかり時間を費やし、現場に携われなくなっていた」
星野さんの中にあった本来のミッションは、組織を大きくすることではない。
子どもの遊び場を作り、現場に関わりながら地域のご縁やコミュニティを作ること。
やがて迎えた2011年3月11日。東日本大震災である。
「これまでは、どう資金を集めるかを考えていたけれど、震災を機にいい意味でリセットされた。自分自身が現場へ行って、子どもたちを応援したり地域と縁をつないだりしたい。そのためにも、助成金に頼らない運営にシフトしなければ」そんな時期が来ていた。
この頃から、東北支援以外の助成金や補助金を受けないことを決め、パートナーシップとの恊働をメインに。
問題は、「どうやりくりするか」だ。
熟考した結果、生まれたのが現在も活動の中で活かされている「かけ算」の法則。
「一個人、一団体だけで活動していると、どうしても限界がある。今まで1万円で受けていたイベントを10万円の価値に高めることは難しい。でも、仲間ひとりひとりのスキルを掛け合わせれば、面白い企画が無限に生まれてくる」
たとえば、建築を学んだ人、絵がうまい人、歌が歌える人―。
それぞれの「得意」をかけ算すれば、2倍にも3倍にも可能性はふくらむ。
個人では成し得なかった、未知なる楽しさを生む“種”になる。
そのことに気づいてから、星野さんは子どもを持つパパ、ママ、地域の学生団体、そしてもちろん子どもたちの個性を
かけ算し、想いやアイデアを“マッチング”することに注力している。

都市化が進むにつれ
希薄になった4つの“間”
星野さんは新潟県妙高市に生まれた。
幼少期を過ごした場所は、山々に囲まれた大自然の中。
熊と出くわしてもおかしくない、都会暮らしから考えれば“何もない”ところだった。
しかし、何もなくても子どもたちにとって自然は格好の遊び場。
子どもは遊びを考える天才である。
落ちている木や葉っぱ、石、何もかもが彼らの遊び道具になった。
探検したり、基地を作ったり、川に潜って魚を捕まえたり、好奇心と工夫しだいで遊びは無限に広がった。
大学進学を機に上京し、都会に暮らしながら星野さんは違和感に気づいた。
それは、子どもや若者たちの“4間(よんま)”の欠如。
「時間」「空間」「仲間」「隙間」
学校の宿題や受験勉強に追われて削られる遊びの時間。
経済的価値の優先により、地域に失われていく遊びの空間。
大人社会の縮図ともいえる、タテヨコナナメの仲間。
忙しない大人の都合に合わせて減っていく心の余裕、隙間。
「子ども時代、遊びを通して学んだことはたくさんある」
大人の価値観からすれば「危ない」遊びも、大人の目を盗んでやり尽くした。
「やってはいけない」ことをやるのが子ども、というイメージは、禁止事項が多い現代において薄れてきていると感じた。
しかし、「子どもは生まれ育つ場所や時代が変われど、根っこは変わらない」と星野さんは言う。
変わったのは、公園の入り口に掲げられた禁止事項のごとく、制限の増え続ける社会とそれに影響されてしまった大人たち。
でも、星野さんは活動を通して感じている。「制限の多い都市部の子どもたちでも、僕ら大人がアホになって『好きに遊んでいいんだよ』と言ってあげさえすれば、彼らの中に眠る遊びの本能は一気に開花するんです」

まち中を遊び場にする!
一台のトラックとの出会い
コドモ・ワカモノまちingがオフィスを構える「3331 Arts Chiyoda(アーツ千代田)」の駐車場に、
一台の変わったトラックが停まっている。
車体には、子どもによるダイナミックな絵が描かれ、荷台には遊び道具がたくさん詰まっている。
道路に絵を描くためのチョーク、懐かしのけん玉、ベーゴマ、何の変哲もない段ボールなど。
このトラックこそが、今の活動の主軸ともいえる「移動式子ども基地」の本体だ。
移動式子ども基地は、「町・地域に子どもの遊び場を出前する」をモットーにしている。
子どもに失われた居場所を与えると同時に、地域のつながりや縁を生み出すコミュニティの役割もある。
日常的に人が行き交う導線上に“遊び場”を開くことで、地域のおじいちゃん、おばあちゃんが声をかけてくれたり、
親同士の交流が生まれたり。
遊び場の片隅に将棋の盤を置いておいただけで、気がつけば通りすがりのおじいちゃんが
子どもに将棋を教えていたこともある。
星野さんが感じた4間の欠如が、移動式子ども基地によって少しずつ埋められつつあった。
このトラックとの出会いは運命的だった。
学生時代、神田で運営していた児童館が再開発のため取り壊されることになったとき。
探しまわっても、同じ条件で借りられる物件は、そうそうなかった。
ある日、星野さんは自動販売機に商品を補填するトラックを見かける。
特殊な荷台の構造に、「巨大なおもちゃの玉手箱だ!」とひらめいた星野さん。
これなら拠点を構えることなく、色んな地域に遊びの出前が可能かもしれない。
しかし、トラックを購入するには、中古でも学生の身分には厳しい100万円が必要だった。
「車といえばトヨタが思い浮かんだ」という星野さんは、ちょうどこの頃、トヨタが公募を行っていた、
地域活動がテーマの助成事業に応募し、思い通じて100万円の寄付を受けることができた。
神田生まれ、缶を運び、感動を生むことから、運命のトラックは「かんちゃん」と名づけられた。
10年経った今も、あちこちを修理されながら現役で活躍している。

街を飛び出した“かんちゃん”
笑顔を届けに東北へ
移動式子ども基地を始めた当初から、星野さんは日本のどこかに“何か”が起こったら、きっと出動することになる。
そう仲間たちに話していた。
そして訪れた2011年3月11日、東日本大震災。子どもたちの公園は跡形もなく流され、
遊び場は仮設住宅へと変わった。
こうなることを予見していた星野さんは、すぐさま“かんちゃん”を運転し、東北の被災地へと走った。
石巻、気仙沼、仙台―。
地震や津波によって壊れてしまった道路を走り、ボロボロになっていくかんちゃんを、
何度も何度も修理しながら。
震災以降、母親の手を一時も離すことができなかった少女が、遊び場で笑顔を取り戻した。
我が子の笑顔を見た母親は、2時間も泣きっぱなしだったという。
また、震災によって所在がわからなくなった人同士が、ふらりと訪れた遊び場で
再会したという話もめずらしくない。
このプロジェクトは「コドモ∞ムゲン プロジェクト」として週に2回、現地に遊びを届けている。
コドモ・ワカモノまちingは、最低でも10年は継続してこの活動に力を注いでいくと決めた。

人と人、人と町をつなぐ
子どもには無限の力がある
子どもの目が輝くのを見たとき、星野さんは活動へのやりがいを感じるという。
そしてもうひとつ。
「出会ったときは小さかった子どもが、若者になって再び僕の元に来てくれたとき。『あの頃、居場所があったおかげで今の自分がいるんです』と言ってくれたときは、最高に幸せでした」
無邪気になって遊んだ子どもが大学生になり、今ではボランティア活動を共にしたり、ときにはお酒を飲み交わすこともある。
星野さんは10年以上にわたる活動を通じて、継続することの意味や大切さをしみじみと感じている。
そして何より、子どもの持つ無限の力を―。
「遊びは国境を越え、世代を越え、ある意味では時間軸をも越えられる。なぜなら遊びは点数によって評価されるものではないから」
多様性のある社会でお互いがお互いを認め合える、それは平和と同じこと。
人と人、人と町は、遊びを通してつながり合えるといっても間違いではない。
遊びの中で発揮される子どもの力は無限だ。
子どもはひとつの物事を多角的に見る才能に長けている。
これこそが、遊びの原点だと星野さんは言う。
それは50年前であろうが、今であろうが変わらない。
課題は、彼らの力を大人がどう引き出し、活かすサポートができるか。
そんなことを日々考えながら、星野さんは今日も日本中の子どもたちの可能性を探している。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
NPO法人コドモ・ワカモノまちing代表理事
星野 諭
2008年にNPO法人化。「遊びは世界を平和にする」をモットーに、遊び、教育、環境、防災、建築、福祉、食、町づくりをテーマとした活動を全国規模で行っている。感動・感性・感謝を育む「感育」を重視し、移動式子ども基地、イベント、キャンプなどを通じて子どもや若者のワクワクする気持ちを引き出し、地域コミュニティを紡いでいくことを目的としている。